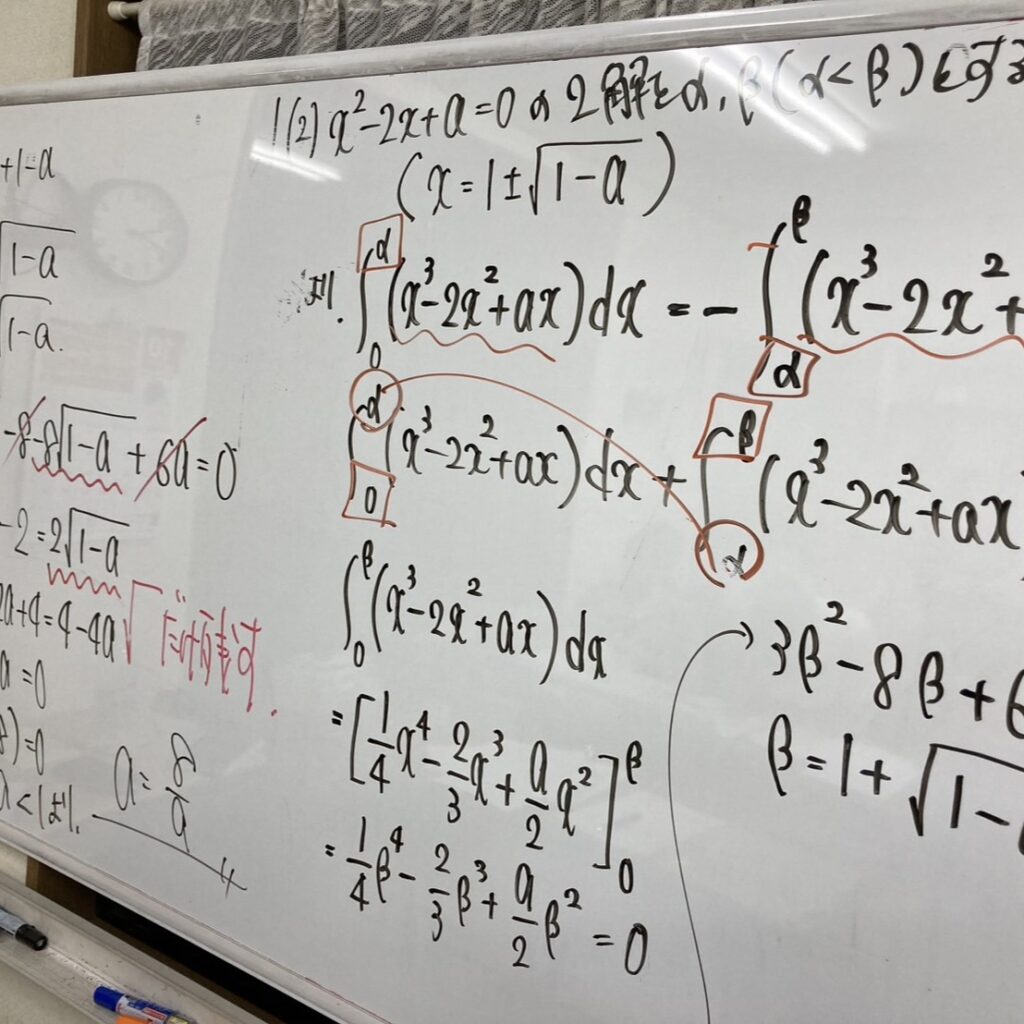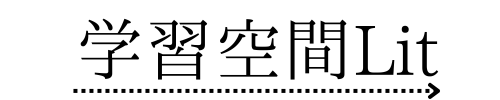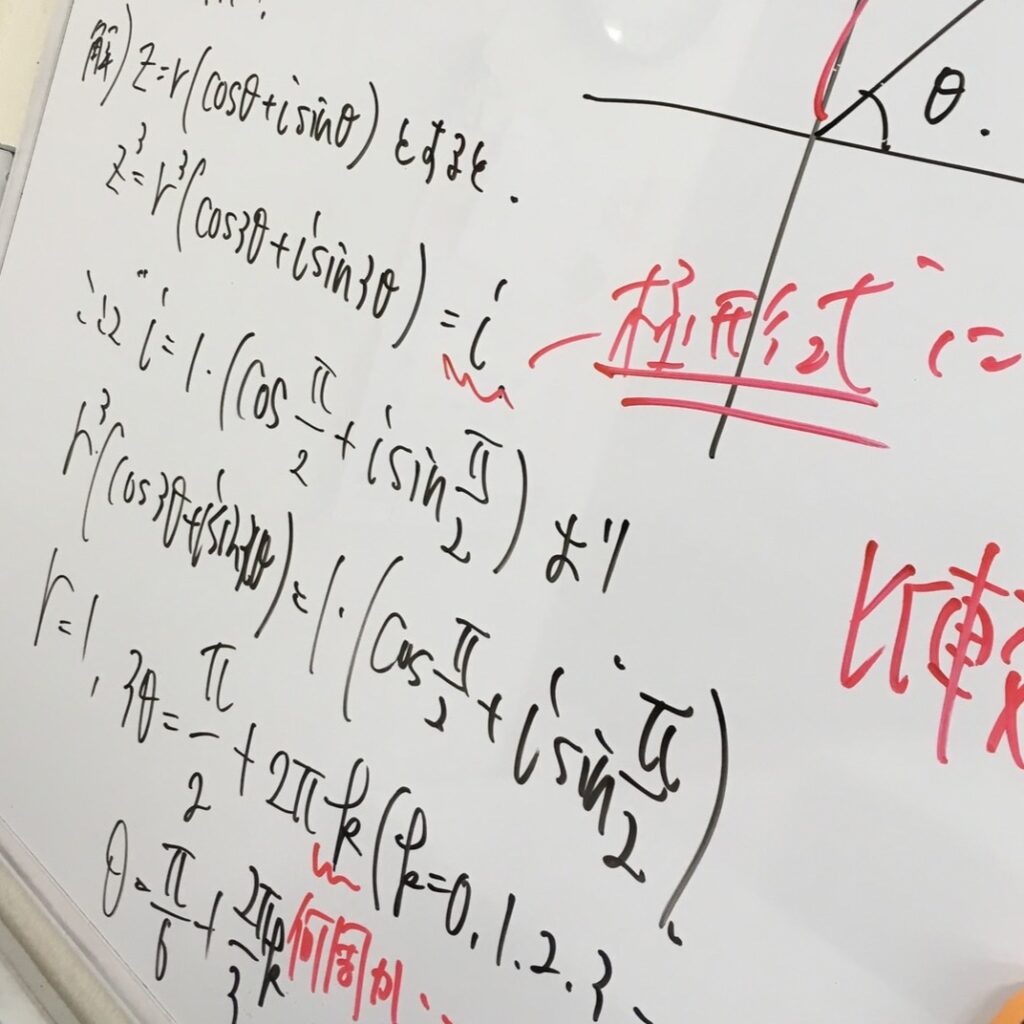
基本的な内容を、基本的な説明とともに、十分な量の演習を積むことで確実に習得してもらえるよう学習指導を行います。この場合の「基本」は決して簡単という意味ではありません。小学校から高校生、その先の学習にまで通ずる、勉強するうえでの土台となるもののことを指します。
全学年を通して意識していることは以下の通り。
- 大学入試まで通ずる勉強観・勉強作法を身につけてもらう
- 授業内での説明を聞いて内容理解してもらえるよう努める
- 質疑応答を軸に授業参加を促す
- 宿題と毎回の小テストで管理能力と確実な復習サイクルをつくる
- 自主性をもって勉強してもらえるよう働きかける
□大学入試まで通ずる勉強観・勉強作法
小学生から高校生まで、大学入試に通ずる勉強観・勉強作法を身につけてもらえるよう指導します。
基本的な内容を安易な暗記に逃げず正しく理解する。暗記から逃げず必要な内容を正しく暗記する。文章の読み方、計算の書き方、〇付けの仕方、解答解説の使い方、やり直しの仕方を正しく身につける。
もちろん生徒全員が大学入試をするわけではありませんし、勉強への向き合い方、その必要性はひとそれぞれです。ですが、正しい勉強観・作法を身につけることは学生のうちはもちろん、大人になっても様々な場面で役に立つと確信しています。
□授業内で説明を完結させる
当たり前のことですが、毎回の授業内で説明を理解してもらえるよう努めます。
とはいえ、時には授業中で説明を理解しきれないということもありえます。そんな時はいつでも気軽に質問しに来るようにと、日ごろから生徒たちに伝えています。安心して遠慮なく声をかけてください。
個別指導は当然ながら、集団授業でも定員12名で、説明を聞く生徒たちの表情を逐一確認しながら説明を行います。講師の一方的な説明にならないよう、生徒の反応を見つつ説明速度や内容の深度を調整していきます。授業内で説明を理解してもらってこその講義です。
□質疑応答こそ学力向上のカギ
当塾の授業では、絶えず講師からの質問・問いかけが飛んできます。授業中に当てられて、講師との質疑応答を行います。
私は、生徒たちの学力向上の大きな要因の一つとなるのはこの質疑応答にあると確信しています。授業での説明を集中して聞き、突然投げかけられた質問に対して適切な回答を考え、その場でことばに表現する。授業中という事情もありますが、ある程度のスピード感をもってこれらの質疑応答を行うことで、ただ授業を受けるよりもさらに思考力が鍛えられます。
中には質問されることや答えることが苦手という子たちもいます。そんなときには適切なヒントや誘導を与えながら、その子の状況・学力に応じた質疑応答を繰り返していきます。
□宿題管理・小テストによる復習サイクル
いくら正しく説明を聞いて授業内で理解したとしても、復習しないのであればせっかくの授業内容を忘れてしまいます。学力向上のために、宿題というものが必要不可欠であるという点を、まずは生徒たちに理解してもらえるよう長期的に説明を尽くします。
毎回の授業では、授業の終わりに適切な量の宿題を提示し、次回の授業で宿題内容から出題される小テストを行います。宿題内容から小テストを行うことで、宿題に対してきちんと取り組む必要性を認識してもらいます。
小テストはただ答えあわせをするだけでなく、採点と同時に行う解説授業で記述のチェック、質疑応答による内容理解の確認を行うため、緊張感をもって準備に臨んでもらえるよう仕向けています。
□自主性にはとことん向き合う
個別指導の生徒も集団授業の生徒も、最終的には一人ひとりに適切な勉強強度や学習量というものが存在します。
- 100の分量をまんべんなく取り組む生徒
- 50の分量を根気強く反復する生徒
- 120の分量で、さらに難しい問題に挑戦する生徒
志望校や勉強における目標がさまざまであるのと同様、勉強の量や方法もまた生徒ごとに異なります。どのような生徒であっても目標に向かって最大限努力していけるよう、日々のコミュニケーションや面談を通じて指導内容を調整していきます。
最後はその子自身がどうしたいのか、どうありたいのか、どうなりたいのか。生徒側の主張をすべて鵜呑みにするわけではありませんが、可能な限り自主性にそった指導であるようとことん向き合い続けます。